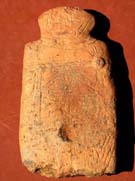|
■飛行機で1時間以上飛び続けても同じような景色が続く巨大遺跡群
な、ナンだ、あの変な景色は!?
アマゾン川源流地帯の上空3000メートルを時速250キロで飛ぶセスナ機の視界に、不思議な地形が近づいてきた!
曲がりくねった川が何本も流れる大平原に、点々と濃い緑の島のようなものが散らばっている。その直径は数十〜数百キロ、高さは
20〜 30メートルほどか。大きさはさまざまだが、どれも日本の古墳に似た人工的な土盛り、“マウンド”に見えた!。
そしてマウンドをとり巻く平原には,もっと仰天させられるものが…。
数キロも離れたマウンド間を結ぶように、正確な直線が引かれていたのだ! 大きなマウンドからは10本以上の直線がウニのトゲのように突き出し、遠くのマウンドから延びた直線と、平原のあちこちでクロスしていた。一列に並んだ数個のマウンドを、串刺しダンゴのようにつないだ直線もあった。
双眼鏡をのぞくと、マウンドを覆う森林の下には、整った階段状のスロープが隠れている様子が見えた。どうやら謎の直線の正体は、平原から数メートル高く盛られた幅5〜6メートルの“土手”のようだ。その周りは背丈の低い草地なのに、なぜか土手の上にはヤシなどの樹木が青々と茂っていた。
近くの平原には、一辺数十キロの長方形や四角形の池が数多くある。それらは真っ平らな土地にマウンドと土手を築くために、誰かが大量の土を掘った跡ではないか?
しかし、今はどこにも人影はなく、部分的に崩れたり川の流れで途切れた土手もあった。もし人工物だとしても、かなり古い時代に造られた遺跡に違いなかった。
驚いたことに、マウンドと土手、池がセットになった人工地形は1時間以上飛び続けてもまだ続いていた。だが、この大平原の別の地域には、さらに腰をぬかすような景色が待ちかまえていたのだ!
そいつは、広い草原に緑や茶色の濃淡で浮き出たモザイク模様の地形だった。細長い棒型の図形がぎっしりと寄り集まっている。まるで大地にへばりついた巨大バクテリアのような薄気味悪さだ。高度を下げて近づくと、1本の棒は予想以上に大きく、幅が数十メートル、長さは数百〜2千メートル以上に達していると思われた。その表面にはキラキラと太陽光線を反射する場所がたくさんある。そう、ここは全体的に水びたしの湿原
地帯なのだ。
そして、このモザイク模様の地形も、水蒸気にかすむ地平線の彼方まで延々と広がっていた! とてつもないスケールだ。形からみて、これは“耕作地”の跡なのかもしれない。
さらに別の方角へ進路を変えると、直径数百メートルの円形の堀跡、高さ50メートル近いピラミッド型の小山など、次々に正体不明の人工地形に出くわした。この大平原には、大昔にたくさんの人々が暮らしていた…。そんな確信が強まるばかりだった。
ところが…。誰の目にも古代遺跡だとわかるこれらの人工物は、まだどの国の歴史書にも紹介されていないのだ!
なぜならWPB取材チームが空から見た地域は、これまで“人跡未踏”と信じられてきた、南米大陸中西部ボリビアの「モホス大平原」と呼ばれる大秘境地帯だったからである。
■ナスカ、クスコ…古代アンデス文明はアマゾンからやってきた
日本列島の約3倍の面積を占めるボリビアは、西側3分の1に海抜4千メートルを越
すアンデス山脈がそびえ、東側3分の2に千キロ四方もの熱帯低地が広がっている。その低地の北側半分がアマゾン川源流地帯のモホス大平原である。
この地域は11月から4月までの雨期に大洪水が起きるため、ほとんど農業や牧畜にも利用されていない。空からは草原に見えるが、乾季でも湿原だらけで地上の移動は難しい。しかもジャガーや大蛇アナコンダ、猛毒の昆虫などがうようよいて、先住民でさえ近づかないという。
そんな無人の大平原に古代文明が栄えていたことは、ボリビア国内でもほとんど知られていない。20世紀に少数の考古学者や人類学者が遺跡の存在に気づいたが、調査地域はほんの一部で、正体は依然として謎に包まれている。
しかし数年前から、その壮大な謎解きに取り組んできたのが、立教大学社会学部の実松克義教授(宗教人類学)だ。そして今年、実松教授は遺跡の全体規模を知るための初飛行調査を行った。その貴重な調査にWPB取材チームも同行させていただいた。
2日間で合計7時間をかけて飛んだ範囲は、モホス大平原中央部の小都市トリニダートから半径約3百キロ。東京を基点にすると、仙台・八丈島・佐渡島・名古屋をカバーする広大なエリアだ。ここに無数の古代遺跡が眠っていた。そればかりか、北側のブラジル国境の先まで、遺跡地帯は広がっていることもわかった。
これまで見過ごされてきた世界史上のブラックボックス「モホス古代文明(仮称)」について、実松教授はこう説明する。
「私は1997年から、南米アンデス地域を中心とした先住民族インディオの宗教文化や遺跡などを調べてきました。その結果、“アンデス古代文明”の遠いルーツが、実はボリビア・アマゾンの熱帯低地にあったことを知りました。このモホス古代文明は、優れた土木技術で水をコントロールして、大規模な計画農業を完成させていたようです。つまり“熱帯地域では古代文明は成立しなかった”という通説が、完全に崩れ去るる可能性がでてきたんです」
現在のボリビアとペルーにまたがる山岳地帯では、推定4千〜3千年前頃にいくつかの地域国家が誕生た。だが、そこには大きな謎があった。それらの地域国家は、その登場の初めから、なぜか完成度の高い農業技術や土木技術、土器製作技術などをマスターしていたのである。
また、アンデス西側のナスカ高地でも、2500年前頃に、どこからか優れた測量技術をもつ人々が現れ、モホス大平原の遺跡と似た直線的で幾何学的な“地上絵”を20数キロ四方の平原に描き始めた。そうしたアンデス古代文明の謎めいた登場パターンも、実は彼らがモホス大平原の先行文明(プレ・アンデス文明)を
ベースに急速な発展を遂げたと考えると、納得がいく。「アンデス古代文明は、ワニや大蛇、ジャガーなど、高地にはいない動物を非常に神聖視していました。それも、彼らの祖先がアマゾン地域と深い関係があったからと考えると、つじつまが合うのです」(実松教授)
■古代オリエント文明、そして縄文人も南米大陸に来ていた!?
モホス大平原に眠る数多くの人工地形がプレ・アンデス文明の遺跡ならば、建造年代は4千年以上前になる。では、そのモホス古代文明はいつ頃から存在し、どれほどのスケールを持っていたのか?
今回の飛行調査ルートを案内してくれた、トリニダートの歴史研究家、リカルド氏の説明は予想以上に衝撃的だった!
「確かな発生年代は不明ですが、遅くとも5千年前頃には成立していたでしょう。隣国チリにある8千年前の集落遺跡などにも、文化的影響を及ぼした形跡があることを考えると、それ以前からあった可能性もあります。
この地域で“ロマ”と呼ぶ土盛りは、洪水に備えた古代人の居住地兼農地だったようです。“テラプレン”と呼ばれる長い土手は、雨期でも平原を移動できるように造られた道路網でしょう。今わかっている限り、ロマは約2万カ所、テラプレンの総延長は5千キロ以上。それ以外にも運河網5百キロ、人造湖約2千、養魚場跡5百平方キロ、耕作地跡4万平方熇以上と推定しています。
数年前にはモホス大平原東部の丘陵地帯で、深さ幅約10メートルの長い溝が見つかり、これはなんと直径 80キロの二重リング状の堀跡でした。モホス大平原を中心としたアマゾン源流地域では、世界史上でも最大規模の人力による土木工事と農地開発が数千年間も続けられていたようです」
直径80キロの堀!? つまり円周距離は240キロ以上! しかし、モホス古代文明遺跡のスケールを空からみると、リカルド氏の話しが決して大げさでないことが納得できる。世界4大古代文明が華々しく発展し、日本列島では縄文文化が頂点を迎えた頃、南米アマゾン地域にも巨大な文明社会が生まれていたのだ!
アンデス高地の遺跡調査に力を注いできた、ボリビア国立考古学研究所の所長フレディ・アルセ博士もこう語る。「これまでの発掘調査で、5千年前頃に世界各地の文明集団が南米大陸を訪れていたことがわかりました。例えば古代オリエントの先進的な技術文明などが、南米古代文化の発展に大きな影響を与えた可能性があります。ベニ州(モホス大平原所在地)に残る大規模な農耕遺跡なども、そのひとつだと思われます」
しかし、ここでまた大きな疑問が湧いてくる。大発展を遂げたはずのモホス古代文明は、なぜ遺跡だけを残して消え去ってしまったのか?
それについてアルセ博士は、
「気候変動やアンデス東山麓の火山活動などで、ある時代から農業ができなくなったのでしょう。3600年前頃に、何か大きな自然界の異変が起きたという説もあります。また最近、ベニ州北西部で直径8キロの隕石孔らしき地形が発見されたことも手がかりになるかもしれません」
アルセ博士によると、その隕石落下時期は2万〜5千年前頃。推定破壊力は、戦略核兵器数十〜数百個分に相当する5百〜1万メガトンだったという。もし落下時期が5千年前頃なら、一瞬にしてモホス大平原は不毛の地と化し、住民たちはアンデス方面へ緊急避難したという仮説も成り立つ。ただし実松教授は、他にも滅亡理由があったのではないかと推理している。
「私は隕石衝突や侵略などの“外因説”よりも、あまりにも巨大化したモホス古代文明そのものが崩壊の原因を招いたような気がします。つまり自然環境の大規模な改造が、元々は農業に適していた地域の気候まで激変させてしまったのではないでしょうか。つまり、私が進めているこの古代文明の研究は、実は、生態系の危機に直面した現代世界の問題ともつながっているんです」
だが、本誌がこの文明に興味を抱いたのは、現代に通じる問題を抱えているからだけではない。実は、古代モホス人がわれわれと同じモンゴロイド種族だった可能性があるのだ!
日本列島から2万キロも離れた地球の裏側に栄えたこの古代文明が、日本列島の古代史の謎とも関係がる? その驚くべき事実は、次号で詳しくご報告する!
(当記事は週刊プレイボーイ11月11日発売号掲載)
|
 report.01=2003/11
report.01=2003/11 report.01=2003/11
report.01=2003/11